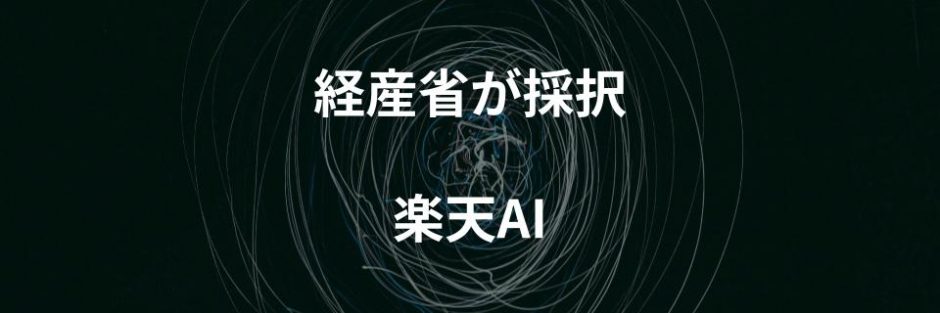この記事では消費者向けサービスから法人向けソリューション、そしてそれらを支える基盤技術である大規模言語モデル(LLM)開発に至るまで、楽天の多岐にわたるAI戦略の全体像を解説します。
また、経済産業省の国家プロジェクト「GENIAC」への採択という最新ニュースについても解説します。
楽天AIとは
楽天のAI戦略は消費者(B2C)と法人(B2B)という二つの異なるターゲットに対し、それぞれのニーズに最適化されたサービスポートフォリオとして展開されています。
消費者向け:Rakuten Link AIによるエンゲージメントの深化
楽天のコンシューマー向けAI戦略の象徴が、楽天モバイル契約者向けに提供されるRakuten Link AIです。
これは、無料通話・メッセージアプリ「Rakuten Link」内に統合されたAIチャットサービスで、ユーザーは追加の登録や費用なしで利用できます。
旅行の計画立案、料理のレシピ提案、文章の要約といった日常的なタスクをサポートするパーソナルアシスタントとして機能し、ユーザーが気軽に最先端のAI技術に触れられるように設計されています。
このサービスの戦略的価値は、単なる無料の便利ツール提供に留まりません。
楽天モバイルの主要なインセンティブである無料通話アプリにAIを組み込むことで、ユーザーは新たなアプリをダウンロードすることなく、日常的にAIと接点を持つことになります。
そして、ユーザーが投じる一つ一つの質問—「週末の旅行先は?」「プレゼントにおすすめは?」—は、楽天にとって顧客の興味、関心、そして潜在的な購買意欲を理解するための貴重なデータとなります。
このデータは、Eコマース、トラベル、金融といった楽天エコシステムのコアサービスにおけるパーソナライゼーションの精度を飛躍的に向上させるための燃料となります。
つまり、Rakuten Link AIは、表向きはユーザーの利便性を高めるサービスでありながら、その実、楽天モバイルの顧客維持率を高め、エコシステム全体のエンゲージメントを強化するための、極めて戦略的なデータ収集・活用メカニズムなのです。
法人向け:事業者とビジネスのエンパワーメント
楽天のAI戦略のもう一つの柱は、法人、特に楽天経済圏を支える膨大な数の出店者や中小企業を対象としたB2Bソリューションです。こちらも複数の階層でサービスが提供されており、企業の規模やニーズに応じた支援体制を構築しています。
RMS AI Assistant: 最も具体的かつ直接的な価値を提供するのが、楽天市場の出店者向け管理システム「RMS(Rakuten Merchant Server)」に組み込まれたRMS AI Assistantです。
これは、リソースが限られがちな出店者の日々の業務をAIで支援するツール群であり、以下のような多岐にわたる機能を提供します。
- データ分析支援 (
データを解説): 売上やアクセス数といった店舗データをAIが分析し、前年比での傾向や特徴を文章で解説します。 - 商品説明文作成支援 (
文章を作成): 商品名やアピールポイント、商品画像をもとに、魅力的な商品説明文を自動生成します。 - 問い合わせ回答生成 (
回答を生成): 顧客からの問い合わせ内容と回答の要点を入力するだけで、丁寧な回答文案を作成します。 - 商品画像加工支援 (
商品画像加工支援AI): 商品画像をアップロードし、テーマを選ぶだけで、AIが利用シーンに合った背景を合成し、魅力的な商品画像を生成します。 - 店舗運営相談 (
AIチャットで質問): RMSの操作方法や店舗運営に関する疑問にAIチャットボットが回答します。
これらの機能は、出店者が直面する「時間と人手の不足」という根本的な課題を直接的に解決します。AIが出店者の業務を効率化し、売上向上に貢献することで、楽天は単なる販売プラットフォームから、ビジネスに不可欠な「業務支援パートナー」へとその役割を進化させます。
これにより、出店者の楽天プラットフォームへの依存度が高まり、競合他社への流出を防ぐ強力な「ロックイン効果」が生まれます。
Rakuten AI (for corporate): より汎用的な法人向けサービスとして、月額1,100円からという低価格で提供されるAIチャットサービスも存在します。楽天モバイルの契約は不要で、中小企業が手軽に生成AIを業務に導入できることを目指しています。営業メールの作成や社内資料の参照など、幅広い業務の効率化を支援し、「AIの民主化」を企業レベルで実現しようとする試みです。
Rakuten AI for Business: ハイエンドなニーズに応えるのが、2023年にOpenAIとの戦略的パートナーシップのもと発表された「Rakuten AI for Business」です。これは、データ分析を行う「Rakuten AI Analyst」、顧客対応を高度化する「Rakuten AI Agent」、社内ナレッジを検索・要約する「Rakuten AI Librarian」といった高度な機能を備え、大企業の営業、マーケティング、戦略策定までを支援する包括的なプラットフォームとして構想されています。
このように、楽天はRMSへの機能統合による深い囲い込みから、低価格な汎用サービスによる裾野の拡大、そしてOpenAIとの協業による高度なソリューション提供まで、多層的なB2B戦略を展開しています。
| サービス名 | 対象ユーザー | 主要な目的 | コストモデル | 主な機能 |
Rakuten Link AI | 楽天モバイル契約者 | ユーザーエンゲージメント向上、データ収集、顧客維持 | 無料 | 日常的な質問応答、文章要約、計画作成支援 |
Rakuten AI (for corporate) | 中小企業を含む全法人 | AIの民主化、業務効率化支援 | 月額1,100円〜(従量課金あり) | 営業メール作成、社内資料参照・抜粋など汎用的なAIチャット |
Rakuten AI for Business | 国内外の企業(特に大企業) | 高度な業務改善、顧客関係強化 | (個別見積もり) | データ分析、高度な顧客対応エージェント、社内ナレッジ検索 |
RMS AI Assistant | 楽天市場出店者 | 店舗運営の効率化、売上向上支援、プラットフォームへのロックイン | (RMS利用料に内包) | 商品説明文・画像生成、データ分析、問い合わせ回答支援 |
楽天市場にも同様のAIを搭載する予定
2025年7月30日、横浜市で開いた人工知能(AI)に関する楽天グループの取り組みを紹介するイベント「Rakuten AI Optimism」で、楽天モバイルが提供しているチャット形式のAI検索サービス(Rakuten Link)を刷新したと発表しました。
電子商取引(EC)サイト「楽天市場」や金融サービスのデータを活用し、利用者の嗜好に沿った回答ができるようにします。
秋には楽天市場にも同様のAIを搭載する予定で、楽天Gの各サービスのデータとAIを組み合わせて楽天経済圏を拡大します。
楽天AI 独自LLMの進化の軌跡
楽天の野心的なAIサービス群は、自社で開発する高度な技術基盤、すなわち独自の大規模言語モデル(LLM)によって支えられています。
その開発の歩みは驚くほど速く、外部技術の活用から最先端アーキテクチャの自社開発へと、短期間で大きな飛躍を遂げています。
その進化の道筋は、2024年3月に発表された「Rakuten AI 7B」から始まります。これは、フランスのAIスタートアップMistral AIの高性能モデル「Mistral-7B-v0.1」を基盤とし、日本語に特化させた70億パラメータのモデルでした。
しかし、楽天は単なる既存モデルの改良に留まりませんでした。
2025年2月、楽天は次世代モデル群「Rakuten AI 2.0」シリーズを発表し、国内外のAIコミュニティに衝撃を与えました。
このシリーズは、性能と効率のバランスを追求した2つのモデルで構成されます。
Rakuten AI 2.0: 高性能な大規模言語モデル(LLM)。Rakuten AI 2.0 mini: 軽量な小規模言語モデル(SLM)で、パラメータ数は15億です。
特に注目すべきは、Rakuten AI 2.0に採用された革新的な技術です。
Mixture of Experts (MoE) アーキテクチャ
Rakuten AI 2.0は、「専門家の混合」を意味するMoEアーキテクチャを採用しています。
これは、一つの巨大な頭脳(モデル)が全てのタスクを処理するのではなく、それぞれが特定の分野を得意とする複数の「専門家(エキスパート)」モデルを束ねるアプローチです。
Rakuten AI 2.0では、70億パラメータを持つエキスパートが8つ搭載されています。
ユーザーからの質問が来ると、「ルーター(ゲーティングメカニズム)」と呼ばれる司令塔が、その質問に最も適したエキスパートをいくつか選択して処理を割り振ります。
この構造の利点は絶大です。モデル全体の総パラメータ数は非常に大きくなるため高い性能が期待できる一方で、一つの処理で実際に稼働するパラメータは一部のエキスパートに限られるため、計算コスト(=運用コストや消費電力)を大幅に抑制できます。
これは、性能と効率というトレードオフの関係にある課題を解決する、極めて巧妙な設計思想です。
Simple Preference Optimization (SimPO)
モデルを人間の意図や好みに沿うように調整(ファインチューニング)する技術も、楽天は最先端のものを取り入れています。それが「SimPO」です。
これは、従来のDPO(Direct Preference Optimization)などの手法と比較して、調整プロセスで別途「参照モデル」を必要としないため、よりシンプルで安定性が高く、計算効率に優れるという特徴があります。
このような最新技術を迅速に採用する姿勢は、楽天の研究開発チームが単なる規模の追求ではなく、実用性、コスト効率、そして性能の最適なバランスを重視していることを示しています。
さらに、楽天はこれらの先進的なモデルを、商用利用も可能なApache 2.0ライセンスのもと、Hugging Faceでオープンソースとして公開しました。
これは、自社の技術力を世界に示すと同時に、国内外の開発者コミュニティに楽天の技術基盤の上で新たなアプリケーションを開発してもらうことを促す、極めて戦略的な一手です。これにより、楽天はエコシステムの拡大、事実上の研究開発の外部化、そして優秀なAI人材の獲得という、複数の果実を同時に手にすることができます。
| モデル名 | 発表時期(推定) | 基盤モデル | パラメータ規模 | 主要アーキテクチャ/技術 | 戦略的意義 |
Rakuten AI 7B | 2024年3月 | Mistral-7B-v0.1 | 70億 | Transformer | 日本語特化LLM開発への本格参入、外部技術の迅速な活用 |
Rakuten AI 2.0 | 2025年2月 | Rakuten AI 7B | 8 x 70億 (MoE) | Mixture of Experts (MoE), SimPO | 性能と効率を両立する独自モデル開発、技術的リーダーシップの確立 |
Rakuten AI 2.0 mini | 2025年2月 | (自社開発) | 15億 | Transformer, SimPO | 軽量・高効率モデルの提供、多様なデバイスへのAI実装を視野に |
| 次世代LLM (GENIAC) | (開発中) | (自社開発) | 7,000億級(目標) | 長期記憶メカニズム | 高度にパーソナライズされたAIエージェントの実現、国家レベルでの開発力強化 |
経産省の生成AIの開発力強化プロジェクト「GENIAC」採択
7,000億パラメータ規模のLLM開発
楽天のAI戦略における最新かつ最も重要な動きが、経済産業省(METI)と新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)が推進する国家プロジェクト「GENIAC(Generative AI Accelerator Challenge)」への採択です。
これは単なる補助金獲得に留まらず、楽天が国内AI開発のトップランナーとして公的に認められ、その野心を実現するための最後のピースを手に入れたことを意味します。
GENIACは、日本の生成AI開発力を国際的なレベルに引き上げることを目的とした国家戦略プロジェクトです。
その支援の核となるのが、LLM開発における最大の障壁である膨大な計算資源(コンピューティングリソース)の確保と、その利用料の補助です。
世界トップクラスのLLMを開発するには、数万基単位の高性能GPUを数ヶ月にわたり稼働させる必要があり、そのコストは数百億円から数千億円に達すると言われています。これは、GoogleやMicrosoftのようなグローバルなハイパースケーラーでなければ捻出が困難な規模であり、多くの企業にとって参入障壁となっていました。
楽天は、このGENIACプロジェクトの第3期採択事業者として選定されました。この国家的な後ろ盾を得て、楽天は2025年8月から、これまでのモデルとは桁違いの7,000億パラメータ規模を持つ次世代LLMの研究開発に着手する方針を固めました。
この動きの戦略的意義は計り知れません。
楽天の最大の強みは、Eコマース、トラベル、金融、モバイルなど、多岐にわたるサービスを通じて蓄積された、グローバルで20億以上(国内で1億以上)の利用者基盤から得られる広範かつ詳細なデータです。このユニークで膨大なデータは、AIモデルを訓練するための最高の「燃料」と言えます。しかし、これまではその燃料を最大限に活用するための巨大な「エンジン」、すなわち計算資源が不足していました。
GENIACへの採択は、この「計算資源のギャップ」を埋める決定的な一手となります。
政府が提供するエンジンと、楽天が持つ独自の燃料を組み合わせることで、同社は単に大規模なだけでなく、日本の言語、文化、そして消費者の行動パターンに深く最適化された、世界にも類を見ないLLMを開発する道筋をつけました。これは、海外製の汎用モデルでは到達し得ないレベルのローカライズと性能を実現し、日本のAI市場において揺るぎない競争優位性を築くための、まさに国家規模の官民連携プロジェクトなのです。
楽天AIの狙い:AIエージェントの創造
楽天が7,000億パラメータという壮大な目標を掲げるのは、LLMそのものの開発が最終目的だからではありません。その強力な頭脳を用いて、楽天エコシステムの最終形とも言える「高度にパーソナライズされたAIエージェント」を創造することこそが、真の狙いなのです。
このAIエージェントのビジョンは、楽天が理念として掲げる「おもてなし」の精神をデジタルの世界で具現化するものです。
それは、単にユーザーの質問に答えるだけでなく、過去の対話や行動を「記憶」し、ユーザーの好みや状況を先読みして、長期的な関係を育むように能動的に提案を行う存在です。
しかし、このビジョンの実現には大きな技術的ハードルが存在します。現在の主流であるTransformerベースのLLMは、一度に扱える情報の量(コンテキストウィンドウ)に限りがあり、過去の対話を永続的に記憶する「長期記憶」が苦手という構造的な課題を抱えています。楽天の次世代LLM開発は、まさにこの課題を克服することを目指しています。
その解決策は、二種類の記憶メカニズムを組み合わせることで実現されます。
- パラメトリックメモリ(内在的記憶): これは、LLMが訓練を通じてそのパラメータ(7,000億個の重み)の内部に蓄える知識のことです。世界の一般的な事実や言語の文法、膨大なテキストから学習した知識がこれにあたります。7,000億という巨大なパラメータは、この内在的記憶の容量と質を飛躍的に向上させます。
- ノンパラメトリックメモリ(外部記憶): こちらが長期記憶と真のパーソナライゼーションの鍵を握ります。RAG(Retrieval-Augmented Generation:検索拡張生成) と呼ばれる技術がその代表例です。RAGは、LLMが回答を生成する際に、リアルタイムで外部のデータベースにアクセスし、関連情報を検索してその内容を回答に反映させる仕組みです。
このRAGを楽天エコシステムに適用した場合を想像してみましょう。AIエージェントは、ユーザーからの質問に対し、7,000億パラメータの汎用知識(パラメトリックメモリ)を使いつつ、同時に楽天のデータベースからそのユーザー個人の最新情報(ノンパラメトリックメモリ)—例えば、過去の購買履歴、閲覧した商品、楽天トラベルでの予約状況、楽天カードの利用明細など—を瞬時に検索します。
具体的には、ユーザーが楽天トラベルでハワイへの航空券を予約した直後、AIエージェントが「ハワイ旅行のご準備ですね。楽天市場で人気の日焼け止めと水着はいかがですか?今なら楽天カードでお支払いいただくとポイントが5倍です」といった提案を能動的に行うことが可能になります。
これは、現在サイロ化されている各サービス(市場、トラベル、カード、銀行、モバイル)を、AIエージェントがハブとなってシームレスに連携させることを意味します。このレベルの統合とハイパーパーソナライゼーションこそが、楽天エコシステムの潜在価値を最大限に引き出し、顧客一人ひとりの生涯価値(LTV)を劇的に向上させます。7,000億パラメータLLMへの巨大な投資は、この最終目標を実現するための、合理的かつ必然的な戦略なのです。
楽天AIの戦略分析と将来展望
楽天のAI戦略は、サービス、技術開発、そしてガバナンスが一体となった、緻密で多層的な構造を持っています。
その全体像を、事業の好循環、競合環境、そして倫理的基盤という三つの視点から分析します。
「AI-nization」フライホイール:価値創造の好循環
楽天のAI戦略の核心には、自己強化的に成長する「フライホイール(はずみ車)」のメカニズムが設計されています。この virtuous cycle(好循環)は、以下の4つのステップで構成されます。
- サービスの提供とエンゲージメント獲得:
Rakuten Link AIやRMS AI Assistantといった消費者・法人向けAIサービス(第1章)が、ユーザーの利便性と事業者の生産性を向上させ、楽天エコシステム内での活動を活発化させます。 - 独自データの生成: これらの活発な利用が、ユーザーの行動、好み、意図に関する他社にはない広範かつ詳細な独自データを日々生成します。
- モデルの継続的改善: 生成された膨大なデータは、楽天の独自LLM(第2章)を訓練・改善するための最高の燃料となります。特に日本語の文脈やニュアンスにおいて、海外製モデルを凌駕する精度と性能の源泉となります。
- サービスの高度化: 改善された高性能モデルが再びサービス群にフィードバックされ、AIエージェントのパーソナライゼーション精度(第4章)が向上します。これにより、ユーザー体験がさらに向上し、最初のステップであるエンゲージメントがより一層強化されます。
このフライホイールが高速で回転し始めることで、楽天のAIは競合に対する持続的な優位性を確立していきます。
日本のAI巨人たち
日本のAI開発競争は、楽天、ソフトバンク、NTTという三つの巨大企業グループを中心に展開されています。各社のアプローチは異なり、それぞれの強みを活かした独自の戦略を追求しています。
- 楽天: 「データとエコシステム統合」 戦略。20億を超えるグローバルな利用者基盤から得られる膨大なデータを活用し、ハイパーパーソナライズされたAIエージェントの構築を目指します。モデルをオープンソース化することで、開発者コミュニティを巻き込み、エコシステムを外部にも広げようとしています。
- ソフトバンク: 「インフラと規模」 戦略。国内最大級のAI計算基盤への巨額投資を背景に、最終的には1兆パラメータ級の超大規模LLM開発を目指します。OpenAIとの強固なパートナーシップも特徴で、AI時代のインフラ提供者としての地位を狙っています。
- NTT: 「効率とマルチモーダル」 戦略。軽量かつ低消費電力なLLM「tsuzumi」を開発しました。高い日本語性能に加え、図表やグラフといった視覚情報も理解できる「マルチモーダル」性能を強みとし、特定の法人向けユースケースに特化して、コスト効率の高いソリューションを提供します。
この競争環境において、楽天の戦略は自社の核となる資産、すなわち「データ」を最大限に活用する点で際立っています。
| 企業名 | 主要LLM | 主要戦略 | パラメータ規模(公表値) | 主要パートナー |
| 楽天 | Rakuten AI 2.0 / 次世代LLM | データとエコシステム統合、パーソナライズ | 8x7B (MoE) / 7,000億級(目標) | OpenAI, Mistral AI, NEDO/METI |
| ソフトバンク | (自社開発LLM) | インフラと規模、グローバル連携 | 3,900億 / 1兆級(目標) | OpenAI, NVIDIA |
| NTT | tsuzumi | 効率、マルチモーダル、法人特化 | 70億 / 6億 | Microsoft |
| サイバーエージェント | OpenCALM / CALM2 | オープンソース、広告技術特化 | 最大130億 | – |
楽天AIの倫理憲章
楽天のAI戦略全体を支える土台が、「責任あるAI」の実現に向けた強固なガバナンス体制です。
その中核をなすのが、楽天グループが策定した「AI倫理憲章」であり、以下の5つの基本原則を定めています。
- 法令遵守と規範形成への寄与: 各国・地域の法令を遵守し、未来のルール作りにも貢献します。
- 人々のエンパワーメント: 人間の創造性を高めるツールとしてAIを設計します。
- 安全性の重視: 開発から運用までの全工程で、厳格なテストと監視により安全を確保します。
- 信頼性と公平性への注力: 公平で偏見のない、信頼できるAIシステムを構築します。
- 透明性による信頼構築: AIモデルの開発・活用方法を明確に説明し、データの収集・利用における透明性を確保します。
ティン・ツァイ氏が率いるCAIDO(Chief AI & Data Officer)組織のもと、AI&データ委員会が設置され、取締役会にも報告されるという明確な監督体制が敷かれています。
この取り組みは、単なるコンプライアンスや企業の社会的責任(CSR)活動ではありません。
楽天のAI戦略が、膨大なパーソナルデータを活用することを前提としている以上、ユーザーからの「信頼」こそが事業の生命線となります。堅牢なガバナンスと透明性の高い倫理基準は、ユーザーが安心してデータを預け、AIエージェントと対話するための絶対的な前提条件です。それは、技術インフラと同等、あるいはそれ以上に重要な戦略的資産であり、楽天が社会から事業継続の承認(Social License to Operate)を得るための礎なのです。
楽天AIのまとめ
楽天グループが推進する「AI-nization」は、単なるスローガンではなく、同社の未来を賭けた包括的かつ緻密な国家戦略です。
消費者向けサービスでエンゲージメントとデータを獲得し、法人向けソリューションでエコシステムの基盤を固め、その両輪から得られる独自の燃料を用いて、世界最先端の独自LLMを開発します。そしてその究極の目標は、楽天の全サービスをシームレスに統合し、一人ひとりのユーザーに「おもてなし」を提供する、パーソナライズされたAIエージェントの実現にあります。
この壮大な構想の実現に向けた最後の、そして最大の障壁であった「計算資源」という壁を打ち破る鍵が、国家プロジェクト「GENIAC」への採択です。これは、楽天が持つ日本最大級のデータ資産の価値を、国家レベルの計算能力によって解放する、まさに決定的な瞬間を意味します。
この官民一体の取り組みを追い風に、楽天はEコマースの巨人から、日本、そして世界をリードするAIエンパワーメントカンパニーへと、その姿を大きく変えようとしています。これから始まる7,000億パラメータ級LLMの開発は、同社の歴史における新たな章の幕開けであり、日本のAI産業全体の未来を占う試金石となるでしょう。